インタビュー

【 どうなる?トラック特集インタビュー・戦国大名に見る増加する情報との向き合い方 】
独自の収集網が必要だ 真偽の判断、相談できる部下と
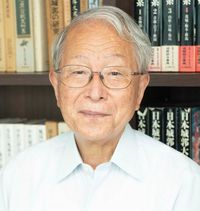
2021年10月19日
小和田 哲男 静岡大学名誉教授
ITの発展でこれまでにない大量の情報が収集・蓄積されている。うまく活用できれば企業は事業を有利に進められる一方、大量の情報にどのように向き合えばよいのか悩む声もある。戦国時代史を研究する小和田哲男静岡大学名誉教授は「戦国大名たちが持っていた独自の情報ネットワークと、真偽を相談できる信頼できる部下の存在が参考になるのではないか」と話す。
勝てる負けるを判断
―戦国大名たちにとって情報とはどのようなものだった。
小和田 戦国時代は日本各地に多数の領国が誕生し、激しい合戦が繰り広げられ、実力主義の世の中だった。こうした時代に戦国大名に重視されていたのは他国の情報だった。中国の兵法書『孫子』の言葉で「彼を知り己を知れば百戦殆(あやう)からず(敵と味方の情勢をよく知って戦えば、何度戦っても敗れることはない)」という言葉があるが、敵対している国の内部の情勢、兵力の動向を把握し、戦を仕掛けて確実に勝てるかどうかを検討していた。
―具体的には。
小和田 例えば、天文24年(1555年)10月に現在の広島県廿日市市の厳島で行われた厳島の戦いで、毛利元就は中国地方を支配していた陶晴賢(すえ・はるかた)を滅ぼした。当時、陶軍の兵力2万人に対して元就軍は4000人と劣勢だったが、陶軍の情勢を見て勝機を確信。少数でも有利に合戦を進められると考え、戦場が狭い厳島に陶軍を誘い込み勝利した。
―他にも好例が。
小和田 永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いも似た構図が見られる。兵力3000人の織田信長に対し今川義元は2万5000人と大きな差があったが、信長が勝利した。信長の家臣で隠密行動をとっていた簗田政綱が、義元軍の人数や動向を信長に提供。桶狭間で休憩していた義元を奇襲した。
秀吉のダイレクトメール
―戦国時代でも情報は大きな影響力を持っていた。
小和田 中でも豊臣秀吉は特に扱いにたけていた。戦わずして勝利を収めるケースもあったほどだ。戦国大名は合戦に勝った時、同盟関係にある大名や家臣に戦勝報告を手紙で伝えることが通例だったが、秀吉は違った。本能寺の変で信長が亡くなった後の後継者を争った賤ケ岳の戦いで柴田勝家を破ると、1度も手紙のやりとりをしたことがない大名にも、戦勝報告を送り付けている。
―どんな意味があったのか。
小和田 信長の実力のある家臣を倒した事実を現代のダイレクトメールのように、無差別に送ることで自身の実力を宣伝する狙いがあった。諸大名に「秀吉にはかなわない」と思い込ませ、戦わずにかぶとを脱がせることに成功し、信長の後継者としての地位を確立した。
―戦国大名たちから現代の経営トップが学ぶべきことは。
小和田 戦国時代に活躍した多くの大名は情報をうまく活用している。諸大名に共通しているのはまず独自の情報源を持っていた点だ。情報量が圧倒的に増えている現代でも参考にできる。
人が足で集めていた
―独自の情報源とは。
小和田 戦国時代にインターネットのような便利なものは存在しない。情報は人が足を使い集めていた。大名たちは、国と国を行き来可能な身分の人を利用していた。代表的なのは僧侶。出家し俗世間とは無縁とされ国境を越えることが容易だった。例えば、元就は琵琶法師数人を手元に置き、国内外に旅をさせて情報を集めさせた。義元は霊山で修行を行う山伏に給料を与え、必要な情報を集めた。
―俗世間から無縁の人材だけだったのか。
小和田 そうではない。国境を行き来できた商人も当てはまる。本能寺の変の直後、徳川家康は信長が亡くなったことを堺で知った。情報を知らせたのは茶屋四郎次郎という京都の商人だった。家康は四郎次郎から物品を購入する代わりに京都の情報を提供させていた。京都が明智光秀の支配下にあることから、京都には向かわず伊賀を経由して本拠地の三河(現在の愛知県岡崎市)に戻った、いわゆる伊賀越えにつながった。
―独自の情報源は現代の経営者にも必要とされる。
小和田 そう。現代では情報があふれ、収集も簡単にできる。だが、その中から経営に有益な情報を得るのは難しい。独自の情報源を持っていることは有利になるだろう。
良いお手本は誰なのか
―真偽の見極めは。
小和田 集めた情報は、次の行動を起こすための判断の材料になるが、まず真偽の見極めが必要になる。だが、情報量が爆発的に増えている現代では、トップが一人で見極めるのは困難だ。判断を信頼して相談できる部下の存在が重要ではないか。260年続いた江戸幕府の礎を築いた家康が好例だ。
―家康はどうだったのか。
小和田 家康には常に相談ができる家臣が多かった。例えば、本多正信は家康に対して意見を述べることができたほか、間違いを指摘できる人物で、情報を判断する際にも相談を受けていたと考えられる。
―信長と秀吉を参考にしている。
小和田 家康は信長と秀吉に仕えていたこともあり、2人を参考にしている。信長はカリスマ性があり独断で判断を下し、部下の意見に耳を傾けない傾向があった。おそらく情報に対しても同じで独自に解釈し独断で決定を下し、家臣に相談するケースはほぼなかったと考えられる。
―秀吉はどうか。
小和田 秀吉の場合、相談ができ意見を得られる家臣が少なかった。秀吉に対して意見や指摘ができた弟の秀長がその役割を担っていたが、全国統一を果たした天正19年(1591年)に秀長が亡くなると、秀吉は大きな支えを失った。翌年には、豊臣政権を衰退させる要因となった朝鮮出兵が始まったが、朝鮮への侵攻に反対していた秀長の死が影響したとみられる。
―理想は家康か。
小和田 そう。先人の失敗は、後の人の教訓になるという意味の「前車の覆(くつがえ)るは後車の戒(いまし)め」ということわざがあるように、家康は信長や秀吉にとどまらず広く歴史を学び先人たちの良い面、悪い面を取り入れていた。こうした姿勢は現代でも通じるものがある。
記者席 頼朝に憧れた家康
「徳川家康は積極的に歴史を学んでいた」。260年続いた江戸幕府の根本をつくり上げ、天下人となった。原動力は何だったのか。家康は若い頃から、源頼朝のようになりたいと考えていた節がある。実際に愛読書の中に『吾妻鏡』があり、「鎌倉幕府を成立させた頼朝を目標として、天下を取ろうとする強い目標を持ちながら頑張っていた」。
現代に視点を移すと、新型コロナウイルスの感染拡大で経済は落ち込み、経営環境が改善する兆しは見えない。「こんな時だからこそ、家康の姿勢は参考にしたい」。厳しい状況でも、企業としての目標や理想とする姿を持つことが大切になる。達成に向けて、何が必要なのか、どんなことができるのか。「考え続けることが経営者には必要ではないか」
