インタビュー

【 特別インタビュー 】
「何を与えられるか」が鍵 〝やりがい〟通じ、負の循環絶て
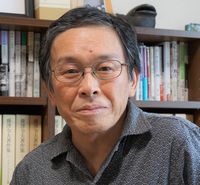
2018年10月09日
哲学・心理学者 岸見 一郎さん
ドライバー不足に苦しむ物流業界。人材が集まる魅力ある職場づくりには何が必要か。経営者に求められることは――。ベストセラー「嫌われる勇気」の著者で哲学・心理学者の岸見一郎氏に処方箋を聞いた。
――物流業界は深刻なドライバー不足に苦しんでいる。
岸見 消費者の立場で言えば、ドライバーに極端な負荷がかかるような行き過ぎたサービスは見直してもいいと思う。本の購入などでインターネット通販をよく利用するが、配達の速さに特段のメリットは感じない。多くの人が同じような意見を持っているのではないか。
――どの辺りが過剰サービスだと感じるのか。
岸見 荷物の種類にもよるのだろうが、一刻も早く届けなければならないと思い込んでいないか。顧客が期待する以上のサービスは控えて、ドライバーの業務を減らす。物流業界に限ったことではないが、社会全体が急ぎ過ぎている気がする。
――宅配便利用時に思うことは。
岸見 マンションの玄関先まで荷物を届けてくれる宅配ドライバーには頭が下がる。こちらが申し訳なくなるぐらいに一生懸命で、いつ休んでいるのか。女性ドライバーがペットボトルの入った重い荷物を担いで3階まで持ってきてくれることもあるが、どう考えてもおかしい。最低限の業務ルールはしっかりと定めておくべきだ。
誰のための働き方改革
――政府主導の「働き方改革」をどう見る。
岸見 ネーミングが良く、労働環境が良くなるように聞こえる。だが、誰のための改革かは判然としない。労働者側はしっかり中身を見極める必要がある。
――強いて言えば。
岸見 残念ながら企業のための改革と言わざるを得ない。高度プロフェッショナル制度では時間に縛られないで働けるというイメージを振りまいているが、果たしてそうか。残業代の支払いは不要になり、残業時間の上限規制はなくなる。高度専門職に就き、年収1075万円以上という要件はあるものの、上限の変更は可能で、高額所得者だけの問題でなくなる可能性が高い。
――時短については。
岸見 残業を望む人は少ないのではないか。お金だけが人生ではない。何のために働くか。いまはライフスタイルに多様性が認められている。
――バランスの問題。
岸見 あくせく働くことだけが幸せな人生ではないということ。また、高給でもやりがいのない職場での仕事は長続きしない。
――時短は稼ぎを減らすという声もある。
岸見 住宅ローンの返済で残業代をあてにして計画を立てた人は、見直しを迫られるかもしれない。だが、時給が安くても残業代で稼げたらいいとするなら、利益に執着する企業の思惑と利害が一致して、負のスパイラルが生まれてしまう。
共同体への「貢献感」を理念に
――何がポイントか。
岸見 大切なのは、労働者がどれだけの価値を提供しているかを知ること。
――では、やりがいとは何か。
岸見 社会、地域、会社など共同体に貢献しているという「貢献感」から生まれるものだ。貢献感とは「何を与えてくれるか」ではなく「何を与えられるか」にあり、あらゆる共同体の中で価値を認め合えれば、人は幸せになれる。
――ドライバー職に当てはめるとどうなる。
岸見 顧客と対面し、反応をじかに受け取れ、「ありがとう」とも言ってもらえる。貢献感が得られやすい職種と言える。少なくとも、幸せを感じられる土台はある方ではないか。
――世間のイメージは良い方ではない。
岸見 3K(きつい・汚い・危険)に代表される負のイメージも、やり方次第で変えられる余地はあると思う。
――経営者に求められることは。
岸見 社会、地域に貢献するという理念を掲げ、理念を業務に反映させた従業員には、見合う報酬を与える。従業員はさらに能力を高めようと自発的に動くようになる。自由闊達(かったつ)な社風とはこうした状況を指すのではないか。
正当な報酬で人材確保
――企業の目的はしばしば利益だといわれる。
岸見 利潤の追求は否定しない。ただし、作為的な「ありがとう」でやりがいを引き出す一方で、給料を安くするというやり方では、いずれ従業員にそっぽを向かれる。例えば、ボランティアは本来志願者という意味であり、無償で働くことではないが、東京五輪の大会組織委員会は募集要項で10日間の拘束を要件とし、酷暑が予想される中での対価はわずか。交通費は1日1000円、宿泊費は支給しない。やりがいの搾取と言える。社会問題にもなっている。
――人材確保は正当な報酬があってこそ。
岸見 職種は違うが、保育所は完全な売り手市場。ある私立の保育所は、保育士の月給を数万円高くして募集をかけた。すると定員の4倍ぐらいの申し込みがあったという。リスクはあるが、報酬の多寡がやりがいを左右するのもまた事実だ。
――最後に競争と協力について。
岸見 競争があるのは当たり前。もう少し踏み込んで協力し合い、価値を共有し合える関係性を培っていく。幸せは労使双方で共通する願いのはず。自己中心的な考えでやりがいを与えつつ安い給料で労働者をこき使う――。働き方改革は本来、こうした負のスパイラルを断ち切るものでなければならない。
