インタビュー

【 3Aキャッチコピー戦略 】
受け取る側の共感誘おう 「運び手目線」の広告
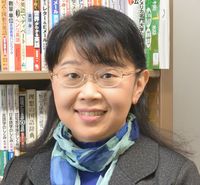
2018年03月20日
中央大学 飯田 朝子 教授
宅配便をはじめとする〝物流危機〟が叫ばれるいま、3A(安全・安心・安定)を目指すトラック運送業界はどんな伝え方でアピールをすれば、社会の物流に対する理解を得られるのか。広告表現の研究に携わりながらコピーライターも務める中央大学の飯田朝子教授に、業界のキャッチコピー戦略について提言をもらった。
日本の物流は真面目すぎ?
――トラック運送業のイメージは。
飯田 きつい仕事で、荷主との上下関係が強いイメージはあります。先日、北陸の大雪でトラックが立ち往生したというテレビのニュースで、やっと解放されたドライバーが「これから荷物を届けに行く」と言ったのを見て、私は気の毒に感じたのですが、学生を交えて話した外国人は「クレージーだ」と言いました。学生も「私だったら家に帰って風呂に入って寝る」と。そのドライバーは疲れ以上に荷物を運べなかった自責の念が強かったのでしょうが、こうした日本人特有の律儀さが、過酷な労働環境や長時間労働につながっているのではとも感じました。
――日本の物流サービスは真面目過ぎる?
飯田 昨年まで2年ほど米国に住んでいましたが、日本との通販サービスの違いに驚かされました。アマゾンで商品を頼むと、「17?21日以内に届きます」という感じで、近所の人たちも「通販だから仕方ない」と割り切り荷物が届くのをのんびり待っている。数時間刻みでモノを届けるという日本の宅配サービスがいかに真面目で、受け取る側もせかせかし過ぎと気付かされました。日本に帰ってからは、荷物を受け取る際、1~2日遅れても仕方がないと思うようになりましたね。
――サービスの見直しも必要。
飯田 ドライバーがプレッシャーを感じない、シンプルなサービスでもいいのでは。ドライバーが「本当の笑顔」でモノを届けられるサービスを目指すことが重要です。いずれ荷物は届くのだから、大きく構えましょうというふうに〝荷物を待つ人の気持ちを和らげる〟広告を展開すれば、物流現場の切羽詰まった状況も緩和されるのではないでしょうか。
「通販中毒」に警鐘を
――具体的なイメージは。
飯田 例えば、「水は小まめを止めましょう」と同じ感じで、スマートフォン(高機能携帯電話)で簡単にモノが買える現状に少し警鐘を鳴らしてみる。「その商品、本当に通販でしか買えませんか」とか「1品ずつ頼むより、まとめて頼んだ方が幸せもまとまる」とか。通販は中毒性が高いので「通販中毒になっていませんか?」と訴えるのもいいでしょうね。
――面白い。
飯田 通販って、お酒を飲んでいる時とかテレビで見た後とか、興奮した状態で買うことが多いですよね。でも1週間たてば実は要らない商品だったと感じるかもしれない。BtoB(企業間取引)の分野でも、「荷物は待つ側にも責任がある」「受け取るまでがあなたの使命」と訴えれば、効果があるのではないでしょうか。
――受取手の意識改革が不可欠に。
飯田 配達の時間指定は「待ち合わせ」と同じ。宅配便再配達が多いという実態も、受け取る側の責任を持って受け取るという意識が薄いからではないかと。私なら、個人でも企業でも発注した側が「受け取る約束」を守ることを認識させるような広告を作りますね。
少し「強烈」な言葉で
――言葉の力もポイント。
飯田 キャッチコピーの機能は、自分には無関係だと思っている人を振り向かせたり、新たなことを気付かせたりすることです。消費者100人に1人に刺さればいいという思いで矢を放つようなものなので、少し強烈な言葉を忍ばせないと、振り向いてもらえません。
――なるほど。
飯田 思い付いたのは、発注者の手元に荷物が届くまでをライブ感覚で見られるコマーシャルですね。駅伝かリレーのようなイメージで、運ぶ苦労を踏まえながら一連の動きを描くことで、見る側が運び手の大変さに共感でき、「頑張れ」と応援したくなるようなCM。見る側が箱の中に入ったような気持ちで、運ぶ人の頑張りを実感できる描き方をしてもいいかもしれない。
――見る側の共感が重要。
飯田 モノが届くことは当たり前ではなく「奇跡」なんだ、と見る側に思わせることが大切。「その奇跡を私たちは演出しています」と締めくくれば、面白いですね。手軽に何でも注文できる時代だからこそ、業界として、受け取る側の気持ちを改革するためのアピールをしていく必要はあると思います。
運び手と荷主は対等
――トラック運送にメッセージを。
飯田 日本の物流システムは完成度が高いと思います。でもサービスにどこまで完璧さを求めるかを見直し、業界で働く人全てが幸せになるように社会構造を変えていく必要はあります。運ぶ側が対等な関係で荷主に物が言え、荷主側も運ぶ人を大切にするような環境になるといいですね。
